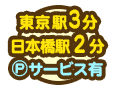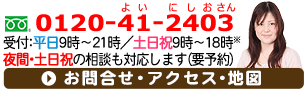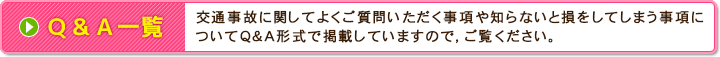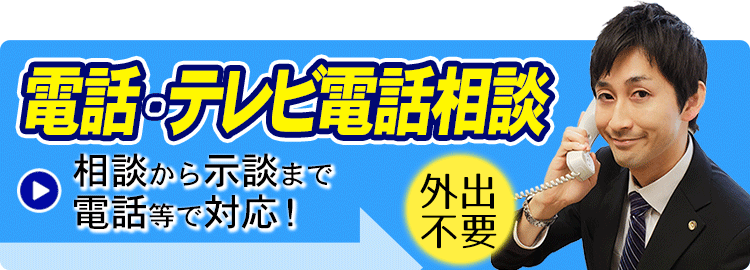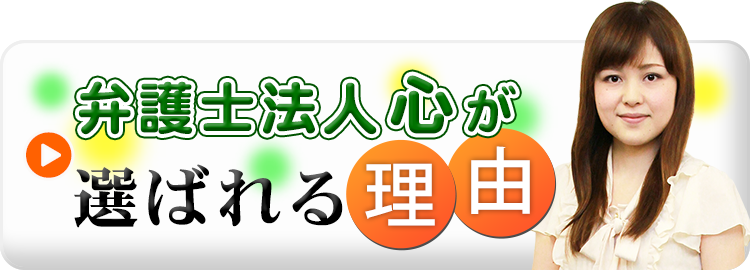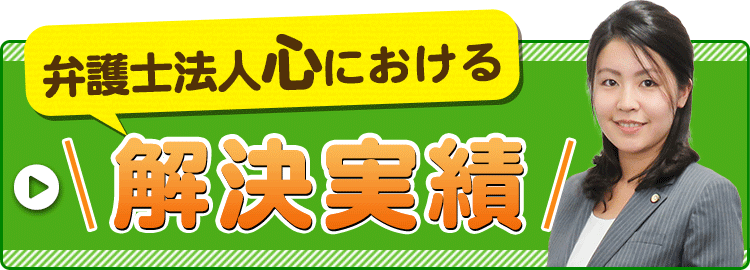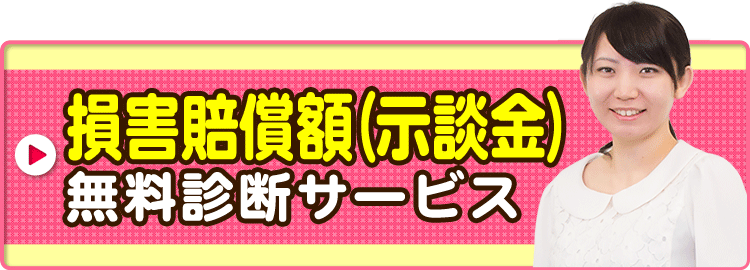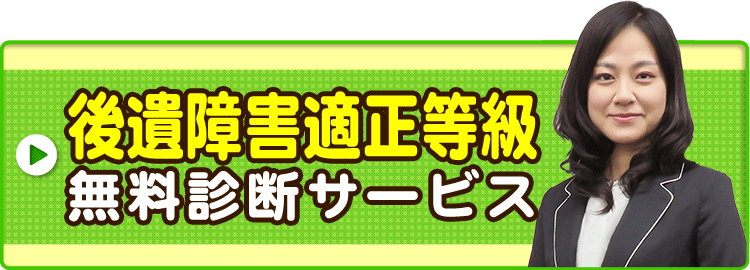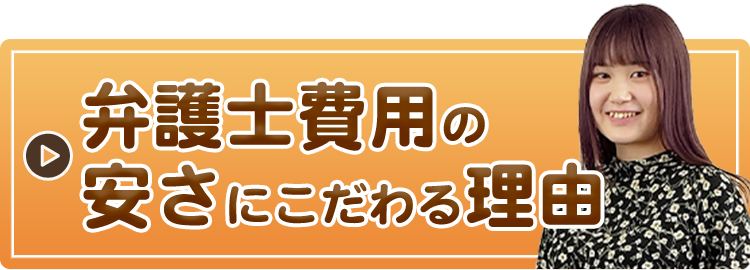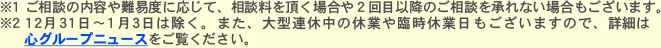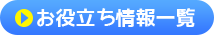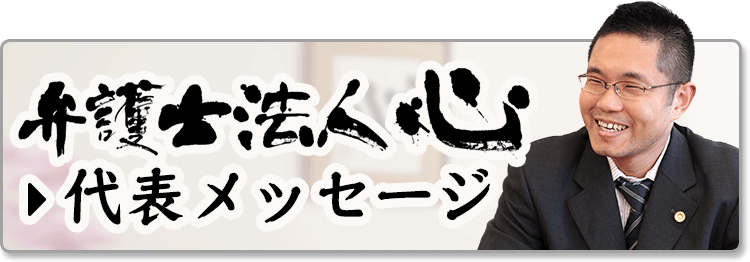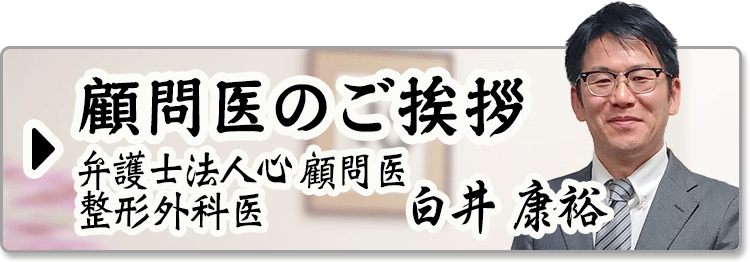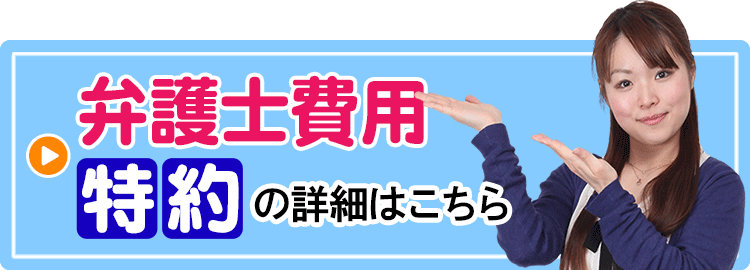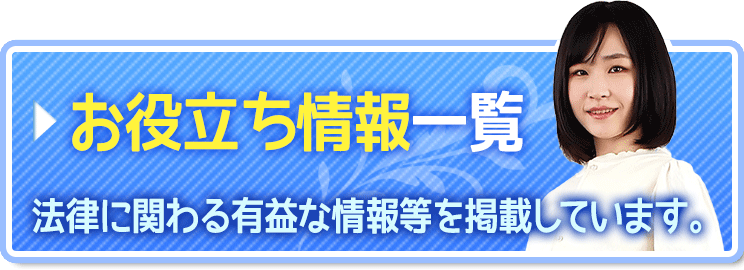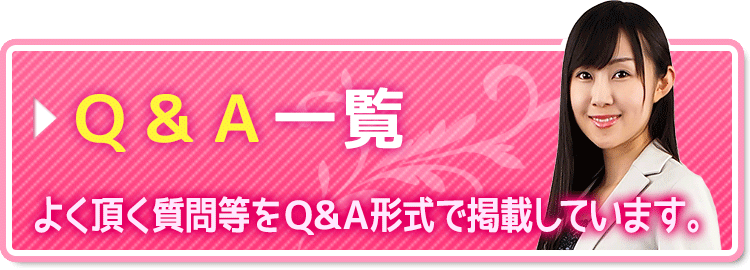死亡事故について
1 はじめに
不幸にして死亡事故が発生し、相手方に賠償請求をする場合、事故の被害者本人ではなく、そのご遺族が、被害者の賠償請求権を相続した上で、請求することとなります。
このため、被害者本人が請求する場合と異なり、以下の対応・準備が必要となります。
2 相続のための手続
⑴ 相続の発生
被害者が死亡した場合、残された遺族自身の慰謝料請求が認められる場合もありますが、請求の大半は、被害者本人に発生した損害(治療費、慰謝料、逸失利益など)を相続した遺族が、その相続分を事故の相手方に請求することになります。
⑵ 損害賠償請求権の相続
ア 相続人間で一般の相続と異なる合意をする場合(例:夫が死亡し、妻と子が残された場合に、妻のみが夫の請求権を相続するとした場合)を除き、亡くなった被害者の賠償請求権は、相続分に応じて、当然に、各相続人が相続し、相手方に請求することができるとされています。
このため、相続人は、戸籍にて被害者の相続人であることを明らかにし、身分証明書(免許証など)により相続人本人であることを相手方に示せば、相手方に相続分を請求することができます。
イ 上記の妻のみが請求する場合などのように、法定の相続分と異なる取り決めをする場合は、相続人全員による遺産分割協議書(遺産全部ではなく、交通事故による損害賠償請求権のみについての分割協議書とすることも可能です。)を作成する必要があります。
請求の際、上記アと同じく、戸籍と身分証明書が必要となります。
3 事故状況の確認について
事故によっては、事故当事者の過失割合(責任の割合)が問題となり、これを明らかにするために事故の状況について確認する必要がある場合があります。
死亡事故の場合、被害者が亡くなっているため、上記の確認が難航する場合もありますが、警察による捜査において、目撃者や事故現場周辺の防犯カメラの画像の確認、現場での確認などが行われ、この資料が公開される場合が多いため、これを手がかりに、事故状況の確認をすることになります。
4 死亡事故による損害について
けがによる損害と異なる部分は、以下のとおりです。
⑴ 慰謝料について
ア 死亡の場合の慰謝料について、なくなった方が、一家の支柱であった場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2500万円、その他を2000万円から2500万円を目安とする取り扱いが行われています。
あくまで目安であるため、最終的な金額は上記と異なる場合もありますが、一家の支柱が最も高い金額とされていることからもわかるように、慰謝料には、残された家族の生活保障のための費用という側面があります。
イ 民法は、死亡した方本人に対する賠償の規定とは別に、死亡した本人の父母、配偶者及び子に対する慰謝料の規定を設けています。
上記の目安となる慰謝料には、死亡した本人と、父母らの慰謝料の合計額を示したものとされています。
⑵ 逸失利益について
ア 逸失利益は、事故により亡くならなければ得られたであろう収入を賠償するものです。
死亡の場合、逸失利益賠償の対象となる収入として、賃金や自営業による収入のほかに、年金もその対象となります。
賃金の場合は就労可能年齢(一般的には67歳)まで、年金は死亡時の年齢に対する平均余命を前提に算定されます。
イ 死亡せずに後遺障害が残った場合も、逸失利益が発生しますが、死亡とけがでは計算方法が異なります。
けがの場合は、後遺障害により見込まれる減収額(年額)に、減収が見込まれる期間に応じた係数を乗じて算定するのに対し、死亡の場合は、生きていたのであれば発生したであろう生活費用を除いた金額に、期間に応じた係数を乗じて計算することとされています。
ただし、個別の生活費を算定することは困難であることから、対象となる収入に、1よりも小さい係数を乗じて、生活費を除いた金額として計算します。
ウ 概ね30歳未満の被害者が死亡した場合、その被害者が収入を得ていたとしても、その金額に基づいて算定するのではなく、労働者全体の平均賃金に基づいて算定することとされています。
これは、若年者の賃金が低く、年齢が上がるにつれて賃金が増加することが一般的であることを踏まえたものです。
⑶ 葬儀費用について
葬儀費用は、亡くなった方により大きく異なるのが実情です。
このため、費用合計額が150万円までは実際に支出した額を損害額とし、150万円以上の場合は、実際に要した費用がこれを上回る場合でも、150万円を上限とする取り扱いが一般的です。
5 弁護士費用について
慰謝料の額からも明らかなように、死亡事故による賠償額は高額となることが多く、これに伴い、弁護士費用も高くなります。
事務所によっては、着手金を0円とし、相手方から賠償金の支払いを受けた際、この中から報酬・費用分の金額を差し引き、その余を依頼者に返金する取り扱いをしている事務所がありますが、このような事務所であれば、依頼の際、金員を工面する必要がないので、負担が軽くなると思います。
また、弁護士費用特約(保険会社が弁護士費用を支払う特約)を用いて依頼する場合、この上限が300万円とされている場合が多いですが、死亡事故の場合、これを超える費用がかかる場合があります。
弁護士費用が高額となった場合の取り扱いについて、依頼する弁護士に確認するようにしてください。
6 おわりに
当法人では、着手金0円でご依頼を受けることができます。
また、交通事故を数多く取り扱っていますので、東京の事務所をはじめ、各事務所の弁護士にご相談ください。
死亡事故を依頼する場合の弁護士費用
1 はじめに

死亡事故の場合、お怪我だけの場合と比べて慰謝料が高額になると共に、生前、仕事で収入を得ていたり主婦として家事を行っていた場合には、逸失利益といって、死亡により得ることができなくなった職業上の収入について、賠償の対象となります。
逸失利益には、年金も含まれます。
多くの場合、死亡に対する慰謝料については1000万円以上となります。
また、逸失利益については、若くして亡くなった場合、利益を得ることができなくなった期間(お仕事(主婦としての家事を含む)による収入の場合、通常は、死亡時から労働可能年齢である67歳まで。)が長いことにより、金額も高額なものとなる傾向があります。
2 弁護士費用特約について
交通事故により死亡した場合、弁護士費用特約が適用される場合があります。
多くの保険会社では、その上限額が300万円とされています。
お怪我だけの場合や、比較的軽い後遺傷害(例:頸椎捻挫後の痛みの残存など)の場合は、弁護士に対する報酬及び事務処理に要する費用を併せても、300万円を超えることはまずありませんが、死亡事故の場合、300万円でも足りない場合があります。
しかし、弁護士費用特約があることにより、費用負担が軽減されることに変わりはありませんので、弁護士に相談される前に、弁護士費用特約が適用されるかどうか、御自身の保険会社担当者に確認されることをお勧めします。
3 賠償額の見通しについて
交通事故の場合、これまで多数の事故が発生し、これに対する賠償が行われてきたことにより、他の事件に比べ、賠償額について同種事案との比較ができやすい状況にあります。
そして、同じ事案でありながら賠償額が異なるといった不公平が起きないよう、賠償の基準について一定の基準が定められています。
このため、確実ではないにせよ、死亡されたときの状況により、賠償額の見通しを立てることが可能です。
これにより、弁護士費用特約の範囲で済むのか、これを超えてしまうのかについて、検討することが可能です。
4 弁護士費用特約を超える報酬及び費用が見込まれる場合の対策
相手方が任意保険に加入しており、賠償額が高額になったとしても同保険からの支払が確実である場合、依頼者の負担を軽減するために、次の方法が考えられます。
すなわち、依頼者と弁護士との合意により、相手方あるいは相手方保険会社より支払われる賠償金を弁護士事務所の預かり金口座に入金するようにします。
そして、入金された賠償金の中から、報酬と費用を弁護士が控除し、その余を依頼者に支払うこととすれば、たとえ弁護士費用特約の上限額を超えたとしても、依頼者が弁護士費用支払のために、別途金員を用意する必要はなくなります。
弁護士費用が高額になりそうな場合は、上記のように、報酬及び費用の後払いについて、依頼する弁護士との間で合意しておくとの方法が考えられます。
5 死亡事故特有の費用(戸籍の取り寄せ費用)
死亡事故を原因とする賠償請求について、多くの場合は、事故により亡くなられた方の賠償請求権を相続人が相続分に応じて相続し、この相続された賠償請求権を、各相続人が行使する(請求する)こととなります。
そして、自身が相続人であることの立証として、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍を全て取り寄せてそろえる必要があるところ、この費用(役所の窓口に支払う手数料、郵送費用など)が必要となります。